スリランカにおける津波意識調査調査結果報告

1.調査概要
1.1 目的
津波に関する危険地域の特定方法および津波に関する知識の普及・啓発方策を提言するために、被災国のコミュニティレベルの防災力の現状および地域特性を明らかにすること。1.2 調査対象地域
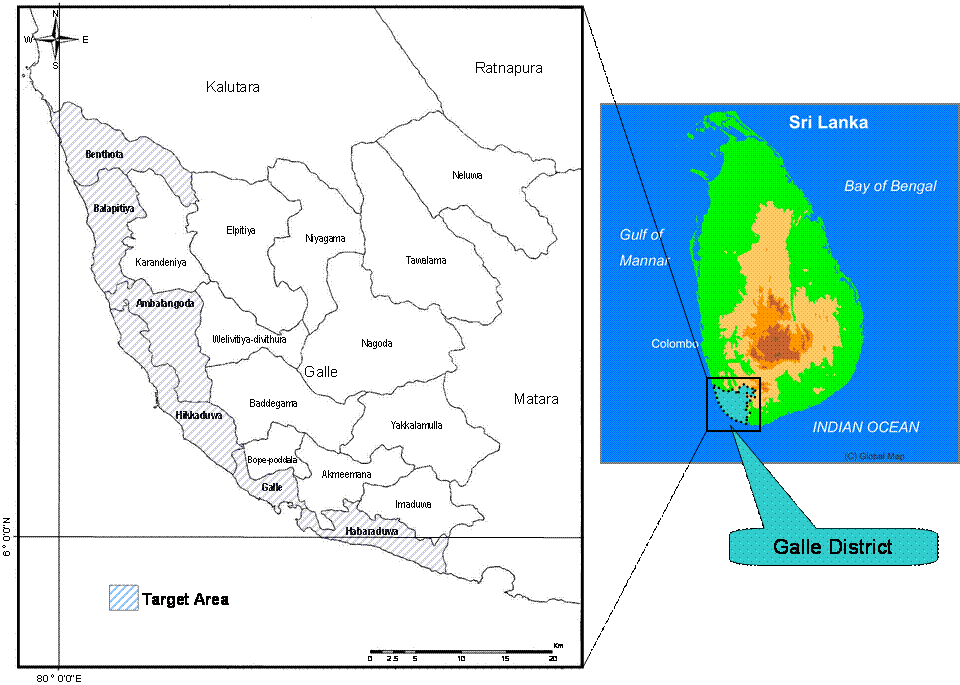
1.3 調査期間
2005年3月2日(水)~12日(土) : ゴール県での調査1.4 調査対象者
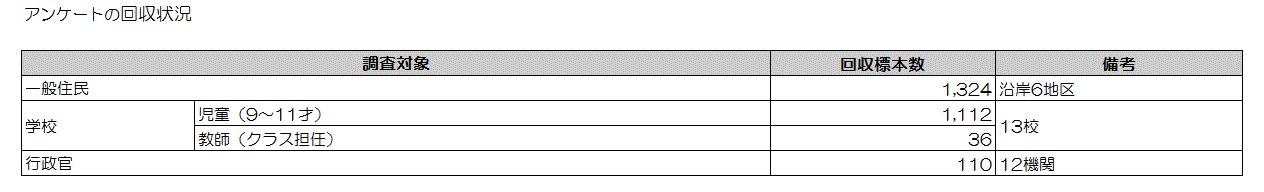
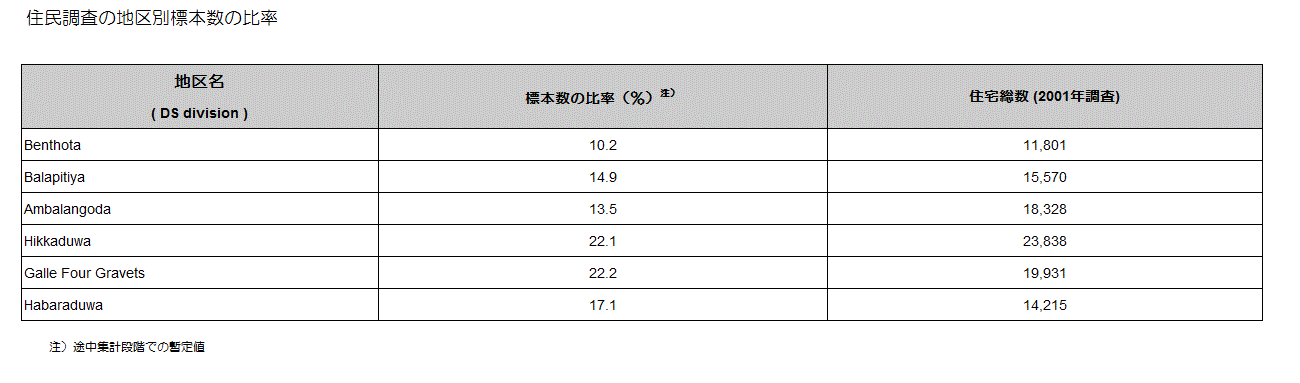
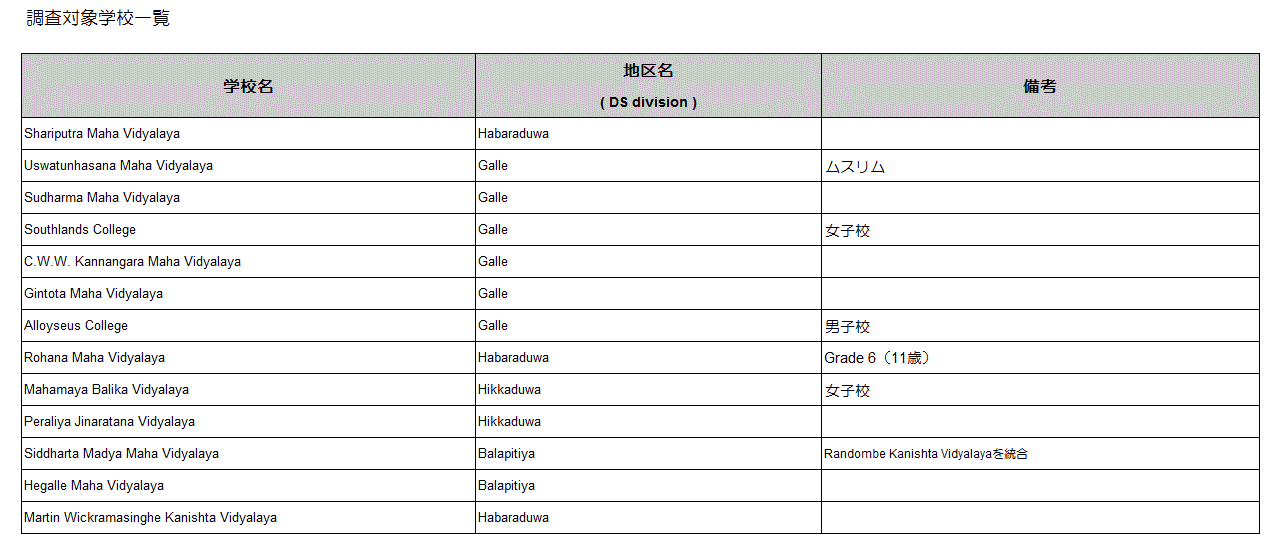
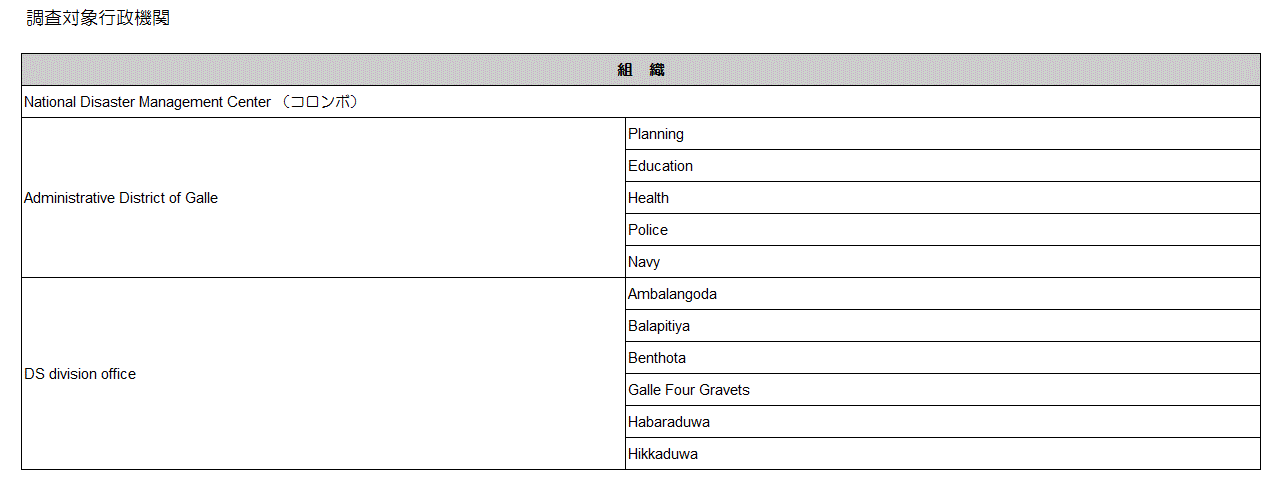
1.5 調査方法
アンケート調査(調査員が直接配布、回収)。一部、調査員が聞き取り。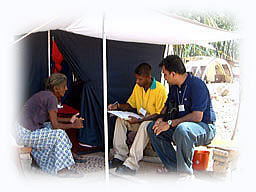
9_11.jpg)
1.6 主な調査事項
〇 一般住民:津波発生時の行動、避難時の情報収集、津波に関する知識、今後必要な対策 等〇 学校児童:自然災害の勉強経験、津波に関する知識、家族との対話 等
〇 学校教師:自然災害カリキュラム、防災用教材 等
〇 行政官 :災害関連研修・訓練、今後必要な対策、観光客対策 等
2.調査結果
2.1 一般住民
標本数:1,324Q. 津波発生時にしたことは何ですか? (複数回答)
(1)波が引いていくのを見て
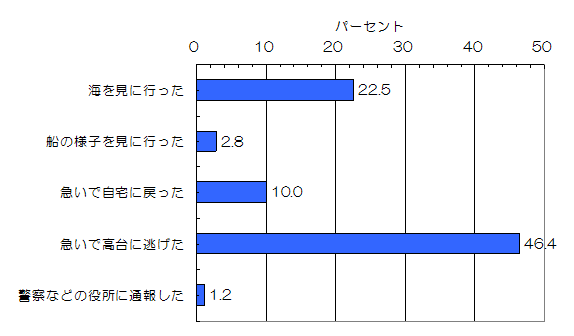
(2)波が海岸に迫ってくるのを見て
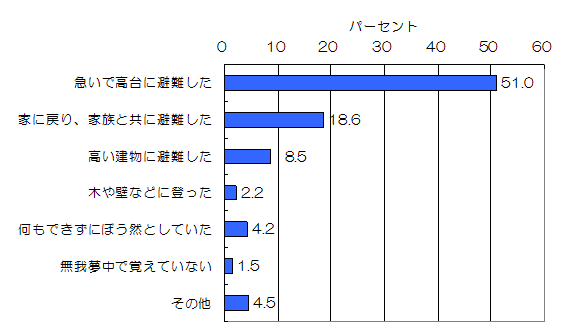
(3)水が自宅や自分に迫って来て
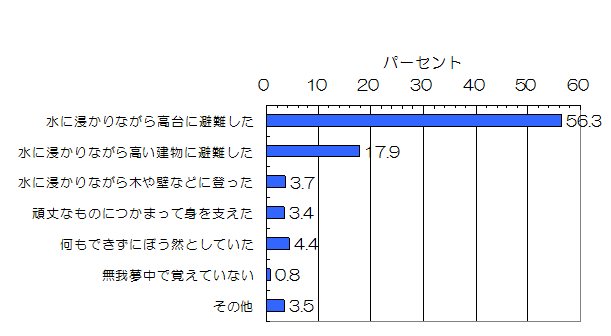
| メモ:殆どの人達が高台等に逃げている一方、引き波時に海を見に行った人がかなりいた。 |
Q. 避難したきっかけは何ですか? (複数回答)
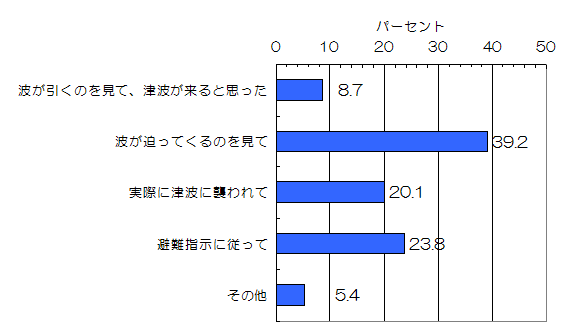
| メモ:多くの人は津波の襲来時に避難している。引き波で逃げた人の数は少ない。 |
Q. どうして津波から助かることができましたか?
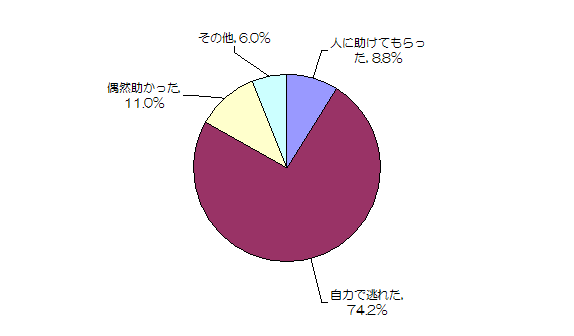
Q. 津波情報をどのようにして知りましたか? (複数回答)
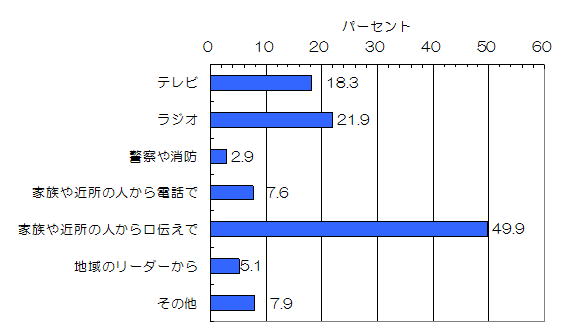
| メモ:多くの人は津波の襲来時に避難している。引き波で逃げた人の数は少ない。 |
Q. 津波発生後一週間くらいの間に、救助・救援に関する情報をどのようにして知りましたか? (複数回答)
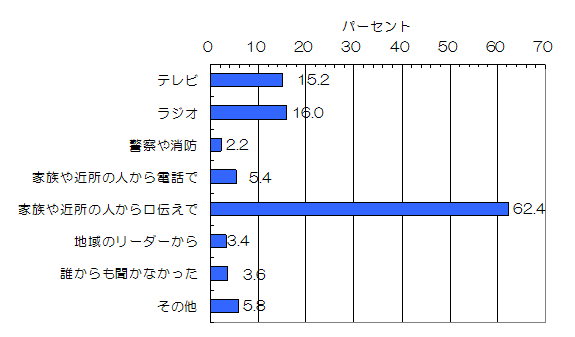
| メモ:情報源としては、マスメディアよりも、家族や近所の人からの伝聞が多い。 |
Q. 津波発生後一週間くらいの間に知りたかった情報は何ですか? (複数回答)
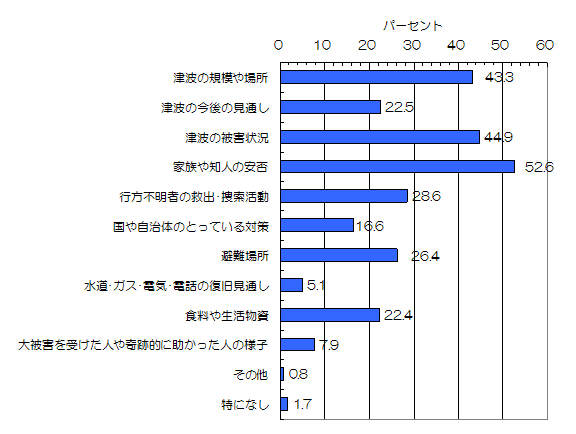
| メモ:家族の安否が多いのは予想通りであるが、津波の規模や被害状況への関心がそれに次いで高く、生活物資や避難場所より上回っている。また、電気・ガス・水道などのライフライン復旧への関心が意外と低い。 |
Q. 知りたかった情報を最も良く伝えたものは何ですか?
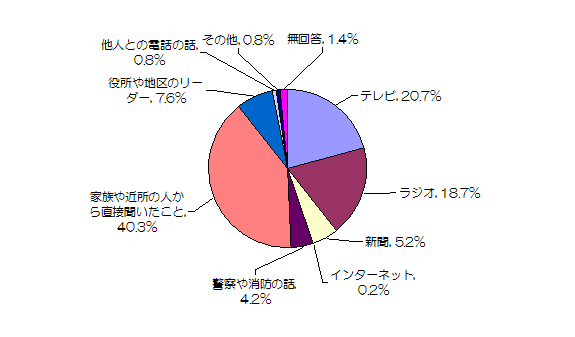
| メモ:知りたかった情報は、マスメディアからよりも、家族や近所の人から得ており、災害時のコミュニティにおける人の繋がりが重要であることを表している。 |
Q. 津波について知っていましたか?
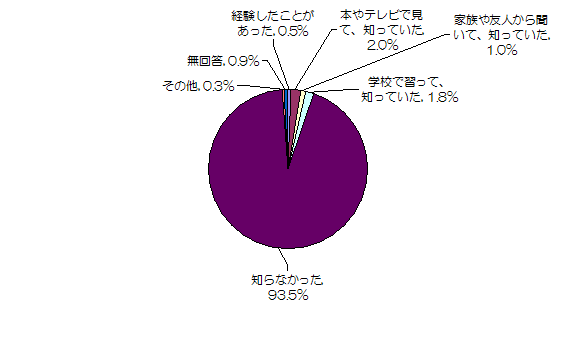
| メモ:多くの人は津波の襲来時に避難している。引き波で逃げた人の数は少ない。 |
Q. もし、津波に関する知識があった場合に、被害は少なくなっていたと思いますか?
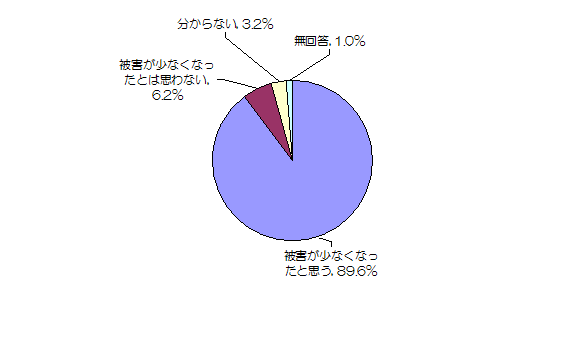
| メモ:防災教育の重要性を表している。 |
Q. 同様の災害を繰り返さないために、人々の防災意識を高めていくのに効果的な方法は何だと思いますか? (複数回答)
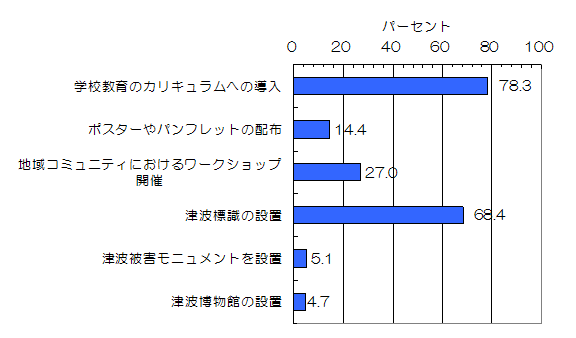
| メモ:学校における防災教育を効果的と考えている人が非常に多い。津波標識の設置が多いのは、実体験(避難時)に基づくものと思われる。 |
Q. 今後の被害軽減の為にどのような対策をとることが必要だと思いますか? (複数回答)
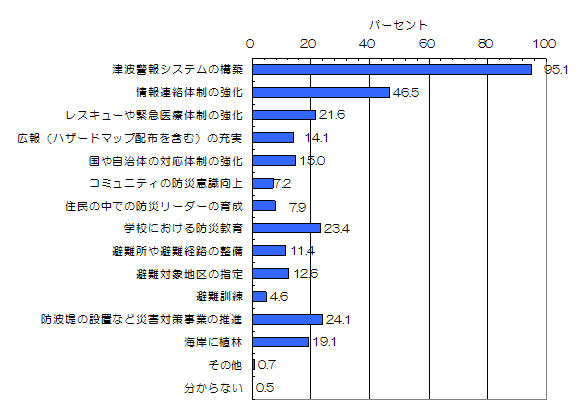
【 標本の基本的特性 】
・年齢構成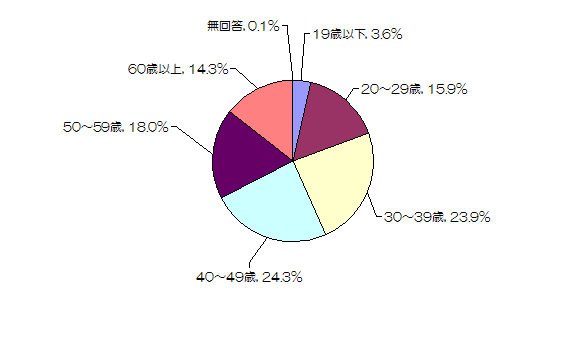
・性別構成
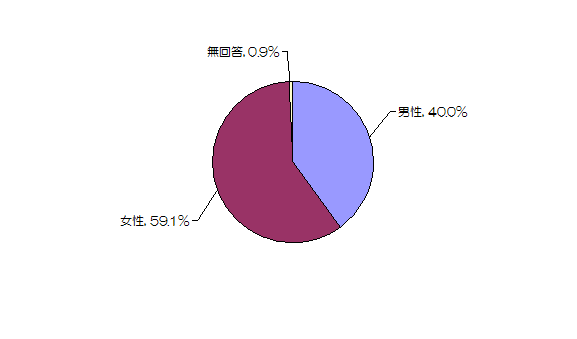
・職業構成
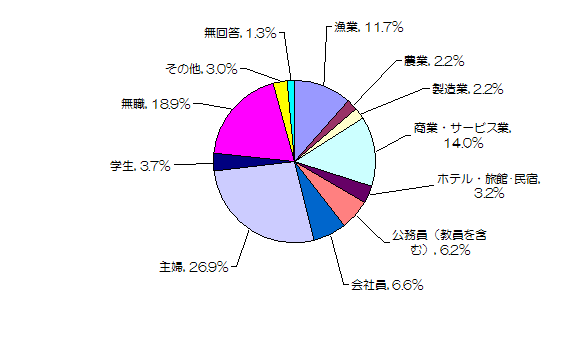
2.2 学校
(1) 児童標本数:1,112
Q. 自然災害(洪水、地滑り、地震、津波)について勉強したことはありますか?
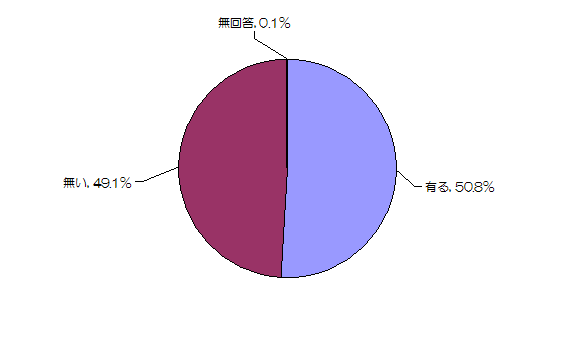
| メモ:学校における本格的な防災教育は行われていない。 |
Q. 自然災害(洪水、地滑り、地震、津波)について勉強したいですか?
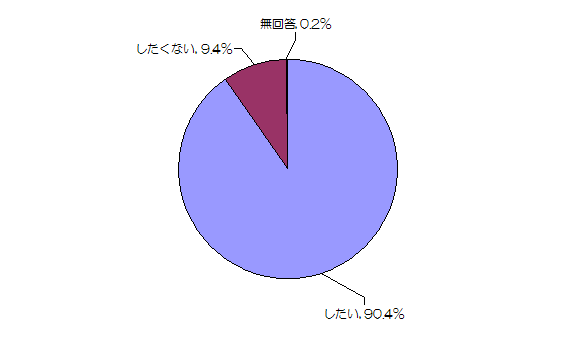
| メモ:現在、子供たちの自然災害への関心は非常に高いことを示している。 |
Q. 津波がなぜ起こるか知っていますか?
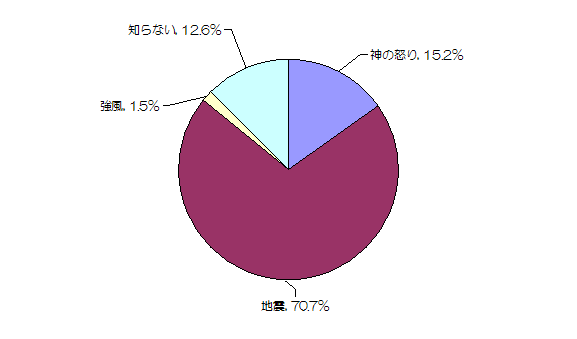
| メモ:津波発生直後にもかかわらず、発生原因を正しく理解していない児童がかなり存在しており、防災教育の必要性が認められる。 |
Q. 海の潮が急に大きく引いた時、あなたはどうしますか?
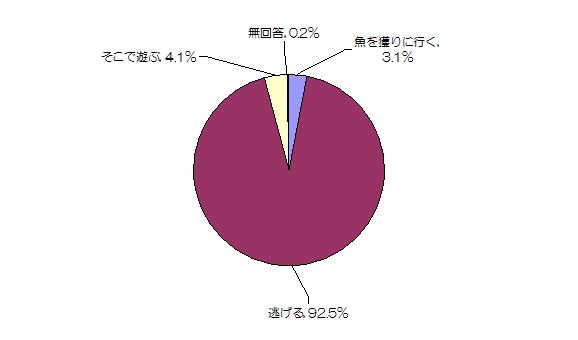
| メモ:殆どの児童は、引き波時の対処の仕方を理解している。 |
Q. 自然災害から身を守る方法について、習ったことは有りますか?
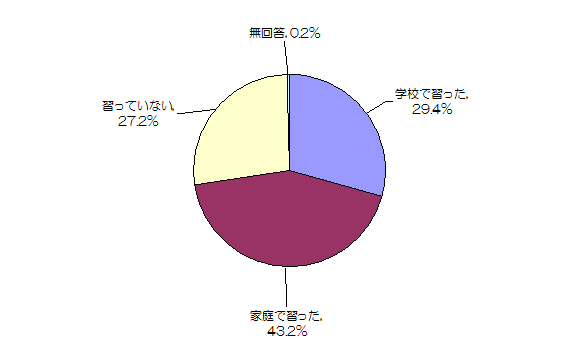
| メモ:学校での防災に関する教育は十分でなく、本格的な防災教育の導入が必要。 |
Q. 学校で習ったことを家で家族と話しますか?
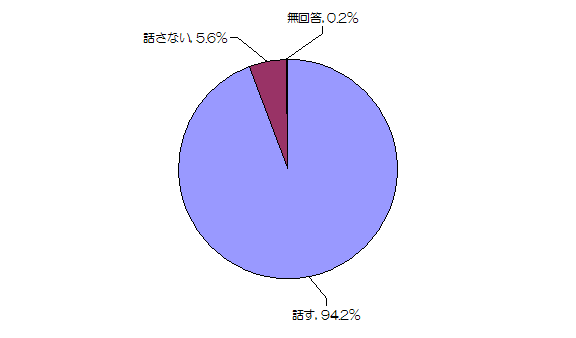
| メモ:学校で防災教育を行うことにより、その効果が大人にも波及することが期待できる。 |
(2) 教師
標本数:36
Q. 自然災害について学ぶ課目はありますか?また、その授業は有効ですか?
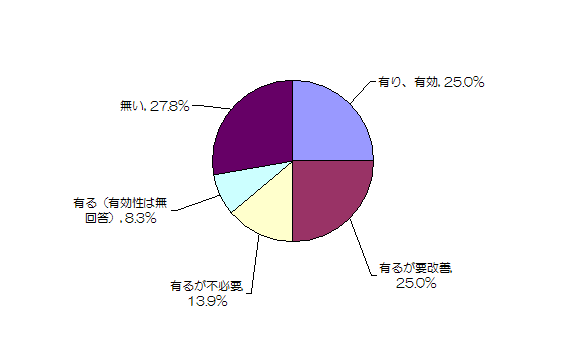
| メモ:有効に機能している自然災害カリキュラムが有るとの回答は全体の1/4に過ぎない。 |
Q. 防災教育用の教材として何が有効だと思いますか? (複数回答)
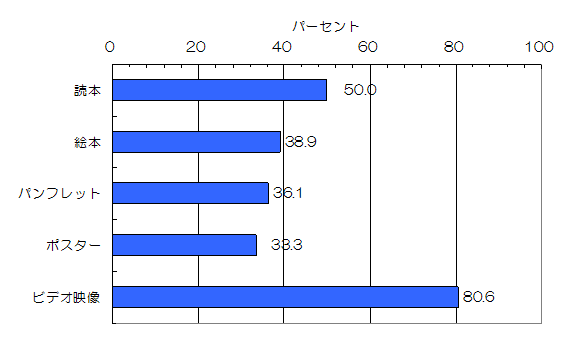
| メモ:ビデオ映像が有効だと考えている人が非常に多い。 |
2.3 行政官
標本数:110Q. 役所における災害に関する研修は有りますか?
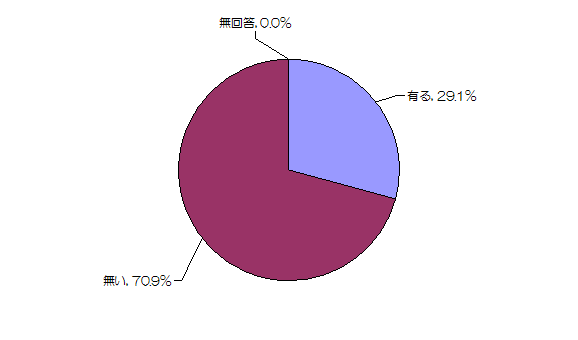
Q. 役所において災害を想定した避難訓練は行われますか?
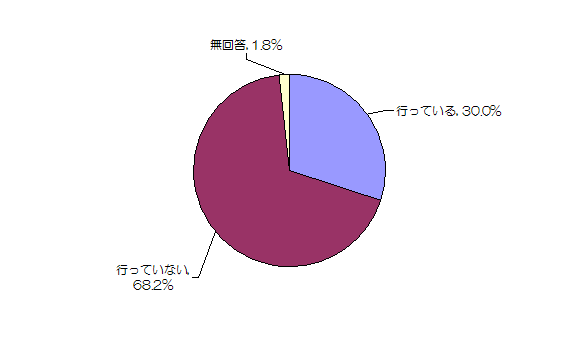
| メモ:両設問で、「Yes」と答えているのは警察の一部と海軍であり、その他の一般の部局では研修も訓練も行われていない。 |
Q. 今後、自然災害による被害を軽減するためにどのような対策が必要と思いますか?(複数回答)
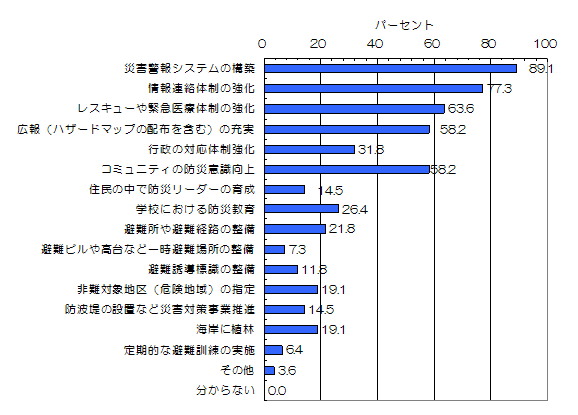
| メモ:警報システム・情報連絡体制の充実、救急体制の強化の他、ハザードマップの配布など広報の充実、コミュニティの防災意識向上が必要と考えている。 |
Q. 災害警報をどのような手段で住民に伝達することが有効だと思いますか?(複数回答)
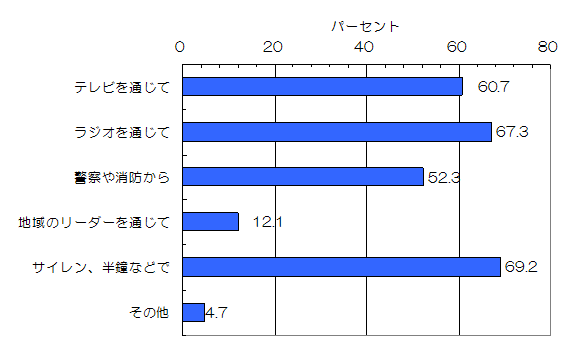
| メモ:サイレンなどが最も多いが、テレビやラジオなども有効だと考えている。 |
Q. 観光客のための被害軽減策は必要だと思いますか?
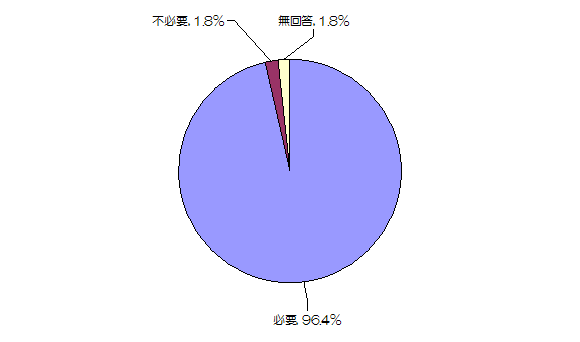
| メモ:Galleは観光地であるため、観光客への対策の必要性を多くの人が感じている。 |
Q. 観光客のための対策として何が必要だと思いますか? (複数回答)
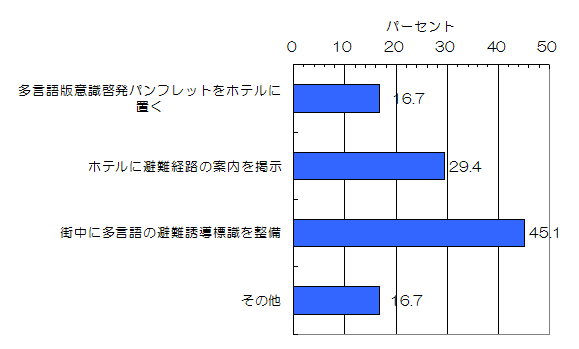
| メモ:避難経路確保に重点をおいている人が多い。 |
2.4 まとめ
(1)一般住民・ |
津波の際、多くの人々が高台等に逃げたが、引き波時に海を見に行った人もかなりいた(23%)。 |
|---|
・ |
94%の住民は津波についての知識が無く、また、90%の人々は津波に関する知識があったなら被害が軽減されていたと考えている。 |
|---|
・ |
津波発生後に知りたかった情報を最も良く伝えたものは、家族や近所の人から直接得た情報(40%)で、テレビ(21%)、ラジオ(19%)、新聞(5%)などのマスメディアを上回っており、コミュニティの繋がりの重要性を表している。 |
|---|
・ |
防災意識の高揚には、学校教育、津波標識の設置が効果的とする回答が多かった。 |
|---|
・ |
今後の被害軽減に必要なものとして、警報システムの構築(95%)、情報連絡体制の強化(49%)、防波堤など災害対策事業の推進(24%)、学校における防災教育(23%)の順であげている。 |
|---|
(2)学校児童
・ |
49%の児童は自然災害に関する勉強経験が無いと答えている。また、90%の児童は自然災害に関する勉強をしたいと思っており、防災教育への関心の高さを示している。 |
|---|
・ |
津波の発生原因について、71%の児童は地震であることを理解しているが、残りの約3割は未だ理解していないのが現状である。以上より、学校教育における防災教育を推進する必要性が認められる。 |
|---|
・ |
94%の児童は学校で習ったことを家族と話しており、学校での防災教育の効果が大人にも波及することが期待できる。 |
|---|
(3)学校教師
・ |
有効に機能している自然災害学習カリキュラムがあると回答した教師は25%に過ぎない。 |
|---|
・ |
防災用教材としては、ビデオ映像(81%)、読本(50%)、絵本(39%)が有効と回答している。 |
|---|
(4)行政官
・ |
役所における自然災害に関する研修は、29%が有ると答えているが、残り71%は無いとしている。有ると答えているのは海軍や警察の一部であるため、一般の行政機関では行われていないのが現状である。 |
|---|
・ |
96%の行政官は、観光客のために被害軽減策の必要性を感じている。具体的な対策としては、街中に多言語の避難誘導標識整備(45%)を多くあげている。 |
|---|
・ |
被害軽減に必要な対策としては、警報システム構築(89%)、情報連絡体制強化(77%)、レスキューや緊急医療体制強化(64%)の順となっており、上位の意見は住民と一致している。この他、ハザードマップの配布など広報の充実(58%)、コミュニティの防災意識向上(58%)が必要と回答している。 |
|---|
・ |
災害警報を住民に伝える手段として、69%がサイレンや半鐘が有効と答えている。この他、テレビ(61%)、ラジオ(67%)も有効と考えている。 |
|---|
3.調査対象地域の被災状況
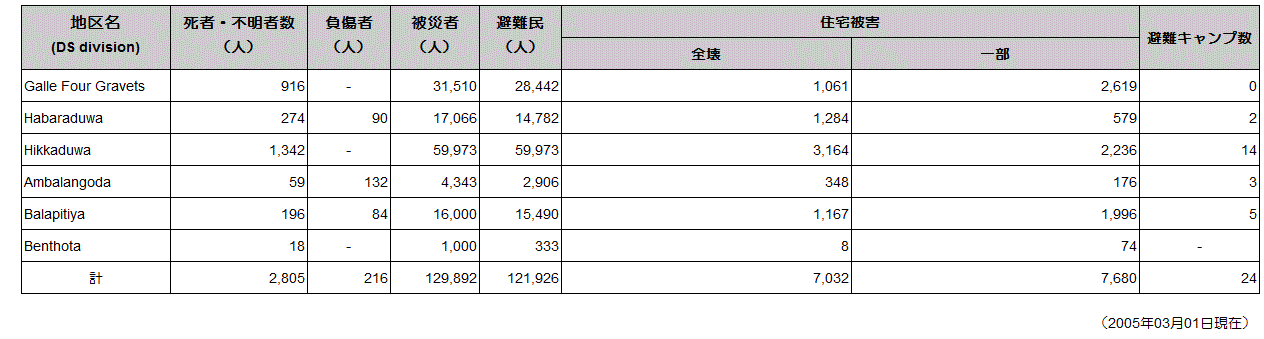


【謝辞】
本調査は、文部科学省の平成16年度科学振興調整費緊急研究「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に関する緊急調査研究」の一部として実施したものです。調査の実施に当たっては、スリランカ政府(NDMC、ゴール県)の協力を得ました。また、コロンボ大学のEdirisinghe氏には、質問票のシンハラ語への翻訳および調査方法に関する有益な助言を頂いた。
Eyecom Lanka Consultancy Services社のPushpakumara 氏には、現地調査のコーディネーションおよび調査団の現地における活動を支援して頂いた。
関係各位に謝意を表します。
【報告書の利用について】
本報告書は、文部科学省の科学技術総合研究委託による委託業務として、アジア防災センターが実施した平成16年度「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に関する緊急調査研究」の成果を取りまとめたものです。従って、本報告書の複製、転載、引用等には文部科学省の承認手続きが必要です。

